![]()
聖歴978年、デュリス大陸全土を治めるサフェイロから2つの国が独立した。1つは元・サフェイロの王女、現国王の異母姉にあたるアムネジアが自らの所領シェロアと周辺の領主を傘下に入れて『アムシスタ』として独立を宣言。その背景にルベリアが関わっていた事から、戦争になればサフェイロが不利になる事を恐れ、独立を許した。それを機に、政府は課税率の引き上げを決定。それに合わせて各地で課税率の引き上げに反対する運動が起こる。政府は騒動の鎮圧に最強といわれる騎士団を派遣するが、将軍・エルシンクは元々、一部の貴族階級や神官、僧侶の思うが侭の政治に不審を抱いていた。派遣された土地の現状を知り、逆に自らが率いる武力で持ってサフェイロからの独立を果たす。国名は『エメルディア』を名乗った。
以前にも増してサフェイロの政治は、宗教色に染まっていった。国王・サリエルは信頼を置く神官・グラツィアの神託により、異常なまでの婚姻を重ねる。
その神託とは――
「卑しい女の腹から王の血を引く神の子が誕生する」
少女はわずか13歳だった。緑の髪に赤の瞳、褐色の肌。腕にはたくさんの細い腕輪が嵌められ、掌には奴隷を意味する焼印が押されていた。
「私はどこへ行く?」
「今の生活よりは随分マシな場所だと思うがね」
僧侶は少女の手を引き、見た事もないような大きな建物の中に連れて行かれた。
「ここ、何?」
「サリエル様の建てられたエヴァミカ大聖堂だ。ここで今から聖なる儀式が行われる。お前はそれを務めてもらうのさ」
大勢の神官たちの前で身を清めるようにいわれ、少女は沐浴をし、身体に香油を塗り、薄い絹でできた装束に着替えた。
禍禍しいほど赤い絨毯の敷き詰められた通路を歩き、促されるままに祭壇へ上がる。祭壇には病的に青白い肌をした男が神官と共に待ち構えていた。男の目は狂っているかのようにギラギラと強い光を湛えていた。
「これより、国王陛下による聖なる婚姻を執り行う」
「さぁさ、陛下」
青白い男はこの国の王だという。少女は神官に促され、訳も分からず祭壇の上に横たわる。
「131人目の妻よ。お前ほど卑しい女なら我が望み叶えられようぞ」
「んんっ…」
言葉は封じられ、衆目の中、その交わりは夜明けまで続いた。
気が付くと、清潔な部屋のベッドに横たわっていた。だが、動こうとして身体が悲鳴を上げた。
「…気が付いたかい?」
「ここは…」
「僕の家。君は今日から僕の妻となる」
そう言って微笑んだのは光のような髪をした美しい青年だった。
「僕の名前はイリア=ローエングラム。階級は騎士だ。君の名前は?」
「…ウルガ。」
「ウルガ。そう、良い名前だね。『シリング』で解くと『蝶』という意味だ」
ウルガは周囲を見渡した。
「大丈夫。もうこれから怖い事は起きない。僕が君を守る」
「…うん。だが…」
ウルガはどうしても昨夜の事が恐怖として焼きついてしまって、イリアの言葉を信じられないでいた。
「イリア!儀式の女を引き受けたというのは本当か!」
「…うるさいのが来たよ。ちょっと、行ってくる」
イリアは席を立って、部屋を出ていった。ウルガは『儀式』という言葉が気になって、今だ重く感じる身体を引き摺りながらその後を尾行けた。
「ジークルード、君は声が大きすぎる」
「…すまん。お前があの狂王から女を下げ渡されたと聞いて…」
「僕は国王に媚びるつもりはないよ。ただ、彼女は今までの女性達と比べてあまりにも幼く、それに擦れていない。儀式にも事情も何も知らされないまま連れてこられたみたいだった。いたいけな少女にこれ以上の酷い事を味あわせたくない。下げ渡され、弄ばれたあげくにボロ屑のように捨てられる女達を今までに何人見た?僕は彼女を…ウルガを守る。そう決めたんだ」
国王の行う聖なる婚姻は一夜のみ。その儀式の後、女達は貴族や僧侶に下げ渡され、さんざん慰み者にされたあげくに捨てられる。今までにも同じように女達を見てきた。だが、イリアはそれを冷めた目で見ていた。ウルガの涙と悲痛な叫びに出会うまでは――。
「ジークルード。僕はおかしいだろうか?」
「…いや。お前の事だ、正しいと思う事にのみ力を注ぐ。『守るものありてこその力と知れ』――お前は見つけた訳だ。守るものを」
「僕は彼女を守る。この身の全てを懸けて――」
ウルガは身体の震えが止まった事に気が付いた。窓から差す光が融けてイリアの髪が優しく染まる。あの温かい光に包まれるなら、どんな闇も怖くない。
「イリア!」
「ウルガ…」
駆け寄ってその胸にしがみついた。
「大丈夫。僕がいる。安心して」
「うん」
「イリア。お前の親友という立場の俺に、お前の花嫁を紹介してくれないのか?」
ジークルードは優しい声音でそう言った。
「紹介するよ。彼はジークルード=レイサム、こう見えても伯爵家のお坊ちゃんなんだよ。ジーク、彼女は僕の妻・ウルガ。仲良くしてあげてね」
「よろしく、ウルガ」
「…よろしく」
ウルガにとって幸せな日々が始まった。イリアとは妻とは名ばかりのまま事のような関係だった。イリアはまだ幼いウルガに手を出す気にはなれず、ままごとのような関係に満足していた。一緒のベッドで眠り、時には読み書きなどこれから必要になる事を教えて過ごした。ウルガは明るさを取り戻し、よく笑うようになった。
――変化は、2ヶ月を過ぎた頃に起きた。
夏になるとサフェイロでもかなり暑い。ウルガは少しまいっていた。
「…もういい」
食欲が落ちてきている。この所、食べるのが苦痛だった。
「食が進まないのかい?」
「ん…」
「果物は?果物くらいは食べられそう?」
「…多分」
イリアの指示でガラスの器に色とりどりの果物が盛付けられたものが運ばれてきた。イリアはその器から1つ摘むとウルガの口へと運んだ。
「どう?おいしい?」
「うん…」
「柑橘系の果物が好きなの?」
「いや…」
言われて初めて気がついた。さっきから柑橘系のものばかりを選んで食べていた。
「恐れながら…奥方は月のモノは…」
給仕をする侍女が声をかけた。
「月の…いや、知らない。随分と来ていない気がする…」
ウルガは記憶を辿ったが、この屋敷に来てから下着を血で汚す事はなかった。
「それでは、もしや…」
侍女は嬉しそうな表情をした。だが、同じ予測のついたイリアは思わず持っていたフォークを落としてしまった。
「まぁ、イリア様。そんなに驚かなくても…」
「…あぁ。そうだな…」
周囲からは仲睦まじい夫婦にしか見えないくらい、イリアはウルガに甘かった。だが、一度だって彼女を抱いた覚えはない。つまり、それは――。
(まさか、あの時の――)
狂った儀式。悪夢のような光景が脳裏を過ぎる。
「お医者様を呼ばなくてはいけませんね…」
「あぁ…」
何も知らないウルガは不思議そうにイリアの顔を見ていた。
![]()
イリアはその日、王宮に居た。
皇后・スヴェナに呼び出しを受けたのだ。
「イリア殿…『光の如き騎士』よ。どうか、妾の話を聞いておくれ…」
皇后・スヴェナは疲れ果てていた。美しい顔もやつれ、もはや別人のようだった。
「妾は道具としてこの宮に嫁いできた。だが、もはやこのような国に価値などがあるだろうか?せめて妾に子でも在らばあの夫を弑すれば事は足りよう?しかし、それは叶わぬ事…ならば、妾に出来る事はただ一つ――この国に妾が嫁いだ時、贈り物の一つとしてもたらされた物の中にこれがある」
スヴェナはイリアに黄金でできた鞘に入った剣を渡した。
「これは――!」
「光の聖剣『ソルフェイド』です。我が祖国トパールに伝わる秘宝の一つ。これをここには置いてゆけません」
スヴェナはヴェールをイリアに与えた。
「さぁ、これを持って王宮を去るのです。これより後は、そなたが所持するように。正しき担い手が現れるまで――どうかそなたの手で守っておくれ…」
「――わかりました。皇后陛下…」
イリアは恭しく礼をするとその場を離れた。剣をヴェールで隠し、王宮を出た。
――その日の夜、皇后・スヴェナ=リフィトゥが自害した。
冬の終わり…それでも雪がちらつく日に、運命の子はこの世に生を受けた。
「イリア様、御立派な男の子ですよ」
生まれたのはウルガにそっくりな男の子だった。緑色の髪、赤の瞳、褐色の肌。あの狂った男の血を受けているとは信じられないほどに清らかで無垢な存在――。
(あぁ、僕はこの子を愛そう…惜しみない愛と与えられる全てをこの子に捧げよう。生まれながらに罪を背負ったものなどこの世には居ない。この子を僕が光の下へ導き、育てていこう…)
イリアは生まれたばかりのその子を抱き上げた。
「エセル…『真実』という名を君に与えよう」
(どんな事実があろうとも、それが『真実』とは限らない。だから、たった一つの『真実』を貫けるよう僕は君を育てる…!)
エセルと名付けられた子はすくすくと育ち、7歳の誕生日を迎えた。
「エセル、今日でお前も7歳か、早いものだ。そろそろ剣の稽古を始めても良い年齢になった」
「はい!」
「騎士となるものは自分の力量に合わせた剣を知っている。決して無理な得物を操ろうと思うな。それぞれに合ったものが必ず正しいんだ」
「はい!」
「まずは剣を選んでくるんだ。自分に合う物を探してきてごらん」
「わかりました!行って参ります、父上!」
エセルは元気良く答えると剣を置いてある武器庫に向かった。そこにはたくさんの武具が置いてある。実はエセルに合わせて作らせた剣が一つだけ置いてある。それを選んでくるのが第一の課題だ。イリアは一生懸命に剣を選ぶエセルの姿を想像して微笑んだ。
(私は幸せだ。国を憂いはするが、私自身は満ち足りている…)
ウルガもすっかり大人びて美しい盛りだ。妻として彼女を愛し、愛され、血は繋がらなくともイリアは可愛い息子にも恵まれた。このまま穏やかに暮らせるなら、騎士としての栄光を捨てても構わないとさえ思った。
「父上!」
エセルが抱えてきたのは黄金の剣。
「エセル…その剣は…!」
「箱の中に入っていました」
それは箱に入れ、厳重に鍵を掛けて封印していたはずのものだった。
「残念だが、それは飾りの剣だ。第一、とても重いだろう?刀身が錆びてしまっているのか鞘から抜けないんだ」
するとエセルは不思議そうな表情をした。イリアはそんなエセルに何故か違和感を覚えた。
「えっ?でも、この剣…とても軽いですし、刀身も錆びていません。ちゃんと鞘から抜く事だって…」
エセルが剣を抜く――光を発しながらするりといとも簡単にそれは抜けた。イリアが何度試しても抜く事ができなかった剣だ。
「エセル…」
イリアはハッとする。違和感の正体は黄金に輝くエセルの瞳だった。
「聖剣の主だと…そういう事か…」
脳裏に不吉な記憶が甦る。
(――神官・グラツィアの神託がこんな形で顕れるなんて…)
「卑しい女の腹から王の血を引く神の子が誕生する」
「エセル…その剣はお前のものだ」
「はい!」
正解を選んできたからだとエセルは喜んでいた。その割に、父の表情がすぐれない。
「父上…お顔の色が…」
「大丈夫だ…大丈夫だよ。エセル…お前は、剣に選ばれた。剣の道とは護りの道。護るべきものを持たない人間は弱い。人間の弱さは時に最大の強さとなる。それをお前に教えよう」
イリアはエセルの頬にそっと触れた。
「いいかい?力とは自ら欲するだけでは手に入らないものなんだ。『力とは、護るべきものありてこそ、その真なる力を知る』――覚えておくんだ」
「誰かの為に強くなれという事ですか?それなら、僕は父上や母上を護れるくらい強くなりたいです」
イリアはエセルを抱きしめる。
(あぁ、神よ…!どうか、この子に光を与えたまえ!どうか――)
黄金の祝福を与えられし運命の子は、同時に黄金の呪縛に囚われる…
『ソルフェイド』――光の聖剣の主には必ず闇が付き纏う。
それは、強すぎる光は他者を傷付ける刃に変わり得るという戒めを顕わしているのかもしれない…。
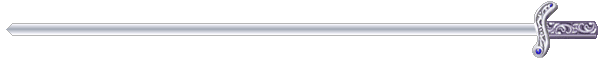 久し振りの更新がこの暗い話かよ…って、これかなり初期に書いたヤツなんです。
久し振りの更新がこの暗い話かよ…って、これかなり初期に書いたヤツなんです。
エセル様の過去はまだまだいっぱいあるのですけどね。
